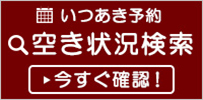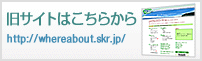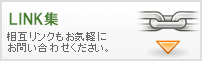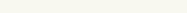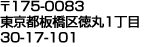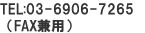自閉症スペクトラム(ASD)
名称が変わりました
日本での診断名は、アメリカの精神医学会が発行している基準マニュアルが使用されています。
最新のバージョンでは、以前使用されていた「広汎性発達障害」が「自閉症スペクトラム」「自閉スペクトラム症」と呼ばれるようになりました。
以前は、アスペルガー症候群と呼ばれていたものも現在は自閉症スペクトラムに統合されています。
最新版はDSM-5ですが、私は比較的「アスペルガー」という言葉をよく使っています。
自閉症スペクトラムの苦手
- 人との関わり方が分からない
- 人の気持ちが分からない
- 相手の立場に立って考えることができない
- 気持ちを上手に伝えることができない
- 想像力が乏しい
- 強いこだわりがある
- 一度に複数の作業をすることができない
- 聴覚・視覚・触覚に過敏 …など
具体的な特徴
- 人との関わり方がよく分からず、周囲から浮いた行動をします。通常よりも社会適応年齢が低いです。
- 作文など自分の気持ちや感想などを表現することが苦手で、具体的でなかったり、何があったのかを説明するときも時系列が前後してしまったり明確でなかったりします。
- 今これをこうすると、この先どうなる?といった先のことなどを想像で考えることが苦手です。
目の前にコップがある⇒手を伸ばすとあたる⇒コップが倒れる⇒飲み物がこぼれる⇒テーブルが汚れる⇒カーペットが汚れる
分かりやすく言うと、こういったことが想像できないということです。 - 誰かと話しているとき、何かをしているときに自分の興味のある対象が目に入ると、そこにとらわれてしまったり、その言葉から他のことを話し出してしまったりします。
結局、もともと何の話をしていたのか?何の作業をしていたのか?忘れてしまいます。 - 色々なところに注目してしまう傾向とは逆に、複数のことを同時に行動に移すことが苦手です。
分かりやすい例ですと、鉛筆を取りにいった「ついでに」鉛筆削りを用意する、シチューを作りながら野菜炒めを作る、といった感じです。 - 赤ちゃんの泣き声、人の話し声、尖ったもの、明るい光、肩を軽くポンとされる、頭を触られる、
など通常では何ら問題のなさそうなことであっても過剰に反応し、嫌がったりします。
遺伝だけでなく「関わり方」と社会も関係しています
発達障害は先天性の障害です。当ルームで対応しているのは”知的障害のないグレーゾーン”の人になります。
また、【大人を対象としたケアの方が】対応のメインとなっております。
相談時には、ご本人の話はもちろんですがご両親についても尋ねることがよくあります。それは多少の遺伝が関係していることも大前提なのですが、それ以上に問題だと思われるのは【親の対応が適切であるかどうか】です。
もちろん親だって初めて親になるのですから何が正解なのかは分かりませんが、それ以前の問題としてこれまで取り扱ってきたケースでは次のようなことが多かったです。
- 親にも発達障害の傾向があって、子育てだけでなく色々な領域での情報の幅が狭い
- 親の苦手が多く、子どもに教えてあげられることが少ない
- 批判・否定などをして子どもを正すことはできるが、褒めることができない
- 子どもの話を聞いてあげることができず、一方的に親の意見を押しつけてしまう
- 何でも先回りして親が決めたり世話をしてしまい、自立の妨げになっている
自覚ある方、無自覚な方いずれも親の立場として問題を抱えているケースです。
親からの観点、子からの観点を含め、当ルームでは【適切な対応法を見出し】また、【適切な課題設定をし】トレーニングとして継続していくことをお勧めしています。
当事者およびそのご家族や、周囲の人たちどなたでもトレーニングが可能です。
AD/HD
AD/HD(注意欠陥多動性障害)の傾向
- 整理整頓が苦手で部屋などが汚い
- 人の話をきちんと聞けずにボーッとしてしまう
- 落ち着きがない
- 周りの音などに敏感で、自分のことに集中できない
- 課題などを仕上げることができない
- 人の話を最後まで聞かずに出し抜けに答えてしまう
- カッとなりやすい
- 失敗しても反省することを忘れてしまっている
- よくしゃべり、止まらなくなってしまう
- 忘れ物が多い
AD/HD(注意欠陥多動性障害)とは 〜特徴〜
「注意性」「多動性」「衝動性」に特徴をもつ症候群です。
幼いころは落ち着きがなく注意力も散漫なのは当たり前のことなのですが、 ここでいうものは【その年齢にはふさわしくない行動】などのことです。
- 人の世話などは得意気にすることができますが、自分の身のまわりのこととなるとできないことが多く、
例えば歯磨き・着替え・でかける支度など、日常に欠かせないことが苦手です。 - 部屋をグルグルと歩き回り続けたり、座って前後左右にゆらゆらしたりします。
- ボタンを見ると反応して押してしまったり特定の何か気に入ったものをコレクションするために、万引きなどやってはいけない行動に出てしまうことがあります。
頭では「いけない」と分かっていても、その行動を抑えることや、気持ちを抑えることができません。 - 何について話し合うかテーマが決まっているとしても、その会話の中に自分の興味のある単語が出てきてしまったとたん話を逸らして違う方向に持っていくことがあります。
周囲はひとまずその話に付き合ったりしますが、結果、何について話していたかを忘れてしまったり、話がまとまらないということがあります。 - 忘れ物、失くし物が多いです。物が落ちた時には音がしますが、通常以上に集中していなければ全く気がつきません。
逆に自分の興味のある音がすると、今やるべきことを忘れてそちらの音に注目します。
例えばお金の音などです。 - 物事の結果を考えることができず、何も考えないで行動に移してしまうことがあります。
そのため道路に突然飛び出して轢かれてしまうなど、取り返しのつかないことが起こることも考えられます。 - 興奮しやすく、自分にとって腹立たしいことがあると、見境なく暴れ出したり暴力をふるうことがあります。
【発達障害全般】気付いたら、小さい頃から療育を
親としては、分かりやすい身体ではなく、分かりにくい障害を抱えていることを受け止めるには勇気も決心も必要になってきます。
障害者というレッテルをはられるのではないかと不安になるかもしれません。
それがきっかけで他の人との差別を受けて辛い思いをするのではないか、いじめにあうなど、返ってマイナスになってしまうのでは・・・などと悲観してしまうかもしれません。
そのため、普通に育てたい、通常学級に行かせたい気持ちから「うちの子供は少し変わっているだけです。問題ありません。」と言われる方がいらっしゃいます。
考え方は人それぞれですから、それで何事もなく大人になるまで成長してくれることが本来はベストだと思います。
ただ、その中には「あの時、早目に受け入れて対応していれば・・・」と後悔される人もいることでしょう。
数十年前と違い、今は発達障害に対して一緒に寄り添ってくれるサポーターが多く存在します。
母親が一人孤独に闘うのではありません。頼れる仲間や、アドバイザーがいることを知っておきましょう。
そして、なぜ早目の療育が良いのかと言いますと、3歳あたりで自分のことを自分で少しずつ始められる頃から、周囲がサポートすることによって本人の習得する期間が短くなるからです。
手先が不器用などのことは、療育でトレーニングを繰り返したりするのですから、早目に越したことはありません。
また、いわゆる「反抗期」に入ってしまうと、本人も人とは違うと分かりながらも認めたくなくなったり、反発することもあるので、その時期に差し掛かることでトレーニングができなくなることがあります。
また、できれば病院を受診しておいた方が良いです。
なぜなら、発達障害に関しては子どもには診断後の療育などケアや支援が充実していますが、大人になってからの発達障害関連では、診断が下りた時に投薬するかどうかというケアがあっても、個別のソーシャルスキルトレーニングなどに対応してくれる機関はまだまだ少ないからです。
ですから15歳になるまでに一度は療育センターなどを受診しておくことで、18歳を過ぎても適切な医療機関や公的機関とつながりを維持できる可能性が高くなるので、支援の手を確保することが大切なのです。
なお、病院受診のメリットとして、投薬を受けることができるということです。
本来、できることなら極力使いたくない薬ではありますが、その薬を投薬することによって、問題行動が減少し、
自分で物事を考えたりトレーニングに前向きになることによって、日々の生活での改善が図れます。
薬は一生飲み続けなくてはならない、とは限りません。
投薬中に成功体験を積み重ねることによって、大きくなってからは薬が無くても成功した体験を思い出しながら
社会で生きていけるということを想定しているのです。